
土地家屋調査士の業務である、筆界確認、土地地積更正登記、土地分筆登記、土地合筆登記、建物表題登記申請等
(詳細は、弊社ホームページ 3. 測量や登記についてののあれこれでご参照下さい)の他、日常でよく取引される形態の
「公簿取引」時にお勧めさせて戴くサービスをこの項では、ご紹介させて戴きます。
「公簿取引」時に於ける弊社「現状把握測量」のお勧め
弊社「現状把握測量」の理念です
我々は、不動産取引の安全と円滑に寄与し社会に貢献致します。
弊社の現状把握測量のご依頼を頂ければ下記のメリットが発生致します。

1. 保険の一つとしてお考え下さい。後々の無用のトラブルを避けて頂けます。
土地売買契約書には、
第2条(公簿売買)
本土地の売買面積は、末尾記載の登記簿上の表示面積によるものとし、本土地の登記簿上の面積と実測面積
とが相違した場合であっても、売主および買主は相互に相手方に対し売買代金の増減等一切異議・請求を
申し述べない。
との記載があると思いますので、基本的にはトラブルにはなり得ないのですが、最高裁判所の
判例でも下記の通り数量指示売買にあたるとして代金減額請求を認めた判例もありますので、
後日のトラブルを避けて頂く為に弊社「現状把握測量」のご依頼を戴きます様、お願い申し
上げます。
判例 最高裁判所 平13.11.22 判事1772-49
判決の要旨 売主、買主共に実測面積が公簿面積に等しいとの認識を有していた事が窺われ、
この公簿面積に坪単価を乗ずる方法により代金額を算定する事を前提にして
坪単価について折衝し代金額の合意に至った事から数量指示売買とみなされ
第一審は請求を斥けたものの控訴審、最高裁ともに売主に代金減額請求を命じた。
国の管理する公の書類である土地登記簿謄本記載面積(公簿)に対する売主様買主様双方の
信頼が厚い為、面積誤差はある程度の範囲に留まっているであろう事を前提として「公簿取引」
がなされていると思われます。もしも買主様売主様が許容範囲と認識しておられる面積誤差を
結果として超えて取引しておられた場合で、買主様が後でその面積誤差を知ってしまわれた場合
に少なからずトラブルになっていると思います。測量してみなければ結果は分かりませんが
後の万一のトラブルが発生した場合の費用と精神的負担を考えれば現状把握測量を保険の一種
としてご依頼戴く価値はあると思います。
2.
スピードがあります。
測量日から約3日で成果品を納品させて戴きます。官民境界確定図がすぐに取得出来ない時
は、その官民箇所は仮で一旦作成して納品させて戴き、取得後出来る限りの復元ラインで
追加納品させて戴きます。
3.
費用が明確です。
どこまでお客様がお求めになられるかにより「松竹梅」の3つのコースをご用意させて戴き
ました。用途と目的に適ったコースをご選択下さい。
隣接土地所有者様との立会確認をする確定測量程の費用が掛からずそれぞれのコースに沿った
内容での物件の現状を把握して戴けます。又、希望によりお支払い時期はご相談に乗らせて
戴きます。
4.
問題点が見つかります。
お取引にあたって買主様が目的を達成する為の問題点が浮き彫りになりますので、その時点で
隣接土地所有者様との立会確認が必要になった時には追加分を別途お見積りさせて戴きます。
又、竹、梅コースであれば越境の可能性のある越境物の調査測量もさせて戴きます。
問題点がなさそうであれば「現状把握測量成果品」を納品させて戴き、作業完了となります。
弊社「現状把握測量図面」を参考資料としてしっかり現状を把握して戴き売主買主双方様が
ご納得戴いた上での「公簿取引」をして戴ければと思います。

「現状把握測量」は売主様、買主様、仲介業者様 3者様にとってそれぞれにメリットがあります。
1. 売主様 費用は多少掛かりますが、最低限度の実測面積が把握出来ますので、実測面積が公簿を
下回った時の訴訟されるリスクが減ります。
買主様に情報が多く伝わり納得して戴け易くなる物件となりますので、結果として
売却出来る可能性が高まりますので、値下げして売却する可能性も下がると思われ
ます。
2. 買主様 最低限度の面積が把握出来、考えておられる建築プランや目的が達成出来ずやむなく
訴訟に至るという不幸な事態を避けて戴け、安心納得して土地購入して戴けます。
又、松コースを選択して戴けましたら高さの要素が入りますので、3次元で対象不動産
を把握して戴けますので、高低差のある土地等土地購入後の建築プランも立てて戴け
易くなりますので、具体的にご検討戴け、よく理解した上での購入の動機付けにも
なります。
3.
仲介業者様 後日の上記訴訟リスクを減少させて戴けます。
又、重要事項説明書作成の一助となります。竹、松コースでは、ブックにして成果品を
お渡しさせて戴きますので、煩雑な資料整理のお役に立ちます。
興味を持たれたお客様により具体的に詳しく物件説明をして戴けますので、
結果として対象物件を売却し易くなるかと思います。
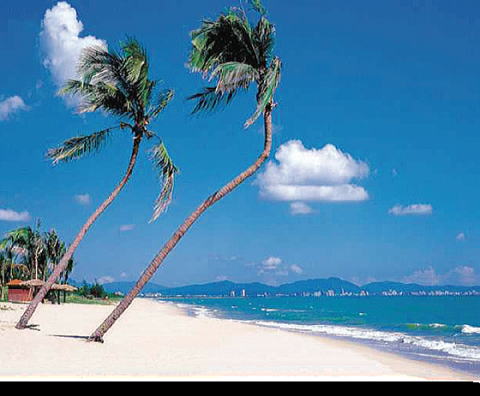
こんな物件は特に「現状把握測量」が得に必要かと思われます。
1. 公図しかない物件
明治時代に測量したままの公簿面積となっています。測量機器の精度も現在とは大分と違いますので、
念の為に現状を把握する為、調査測量をされた方がご賢明かと存じます。
2. 地積測量図が古い物件
ここで地積測量図の概略の歴史をご紹介させて戴きます。
1. 昭和52年9月3日の施行細則で境界標識がある時は地積測量図に記載すべきとされました。
2. 昭和54年4月1日以前の分筆登記は実際に確認したかどうかはともかく法務局としては立会証明書の
提示を求めておりませんでしたので、所有者の境界指示だけで求積した分筆登記も可能でした。
地積更正登記についても公簿より更正後の面積が増える時だけ隣地所有者様の立会証明書が必要
だっただけです。
よって特に分筆登記の地積測量図のある求積土地でも実際と大きくずれている可能性もあります。
3. 昭和54年4月1日以降昭和62年3月1日まで
分筆登記の求積地でも隣接地所有者様の認印をついた立会証明書(図面は無し)が必要と
なりました。
昭和58年の改正でも分筆残地形状も歩測程度で記載が必要となりました。
4. 昭和62年3月1日以降平成5年まで
上記条件の上で図面付の立会証明書が必要となりました。
5. 平成5年から平成11年まで
境界標識の設置が原則となりました。
設置出来ない箇所は引照点(恒久的地物)から境界点までの距離、角度の位置を表す記載が必須
となりましたので、地積測量図に現地復元性を持たせる様になしました。
6. 平成11年以降平成17年まで
隣接地所有者様との筆界線(登記地番同士の境界線)の確認認識合意書類を「筆界確認書」で
統一する事とされました。 それまでは、境界確定協議書等のタイトルもありましたが、
より筆界線に客観性を持たせる為に確認書となりました。
6. 平成17年以降
世界測地系公共基準点からの測量が必要となりました。
又、広い土地から少しの土地だけ分筆する様な特段の事情は無い限り「残地求積」は認められ
なくなりました。その代わり平成18年より筆界特定制度が始まり申請により法務局が筆界を特定
してそのラインで全筆求積をする様になりました。実務上は筆界特定申請書提出後、
カミソリ分筆が認められていますので、筆界特定後地積更正する取扱が可能となっています。
3. 高低差のある物件
断面図作成致しますので、高さだけでなく勾配もはっきり致します。(松の場合に限ります)
法面擁壁の有る宅地であれば「有効宅地面積」も算出致します。(竹、松の場合に限ります)
4. 接道が困難な物件 は路地から接続する本線道路も含んでの現在状況も図示致しますので、
43条但し書き許可申請の協議用図面としても使用して戴けます。(竹、松コースに限ります)
専用通路が必要幅員あるか微妙な物件も詳細測量致します。
5.
土地形状が複雑な物件、家屋が密に建っていて簡単にテープ測量出来ない物件も測量機器で現状を
正確に測量致しますので、より有益となります。
6. 買主様が家屋を建築される可能性が高い物件 2項道路後退後仮面積、勾配のついた法面のある土地の
有効宅地面積、用途地域の分かれている土地はそれぞれの用途地域毎の仮面積 も出させて戴きます
ので建ぺい率と容積率の仮計算にもお役に立ちます。(竹と松のみ)

ケースにあわせて弊社「現状把握測量」を
「保険機能を併せ持った土地販売促進ツール」としてどうかご利用下さい。
楽曲は、ショパン 「ノクターン 第2番」