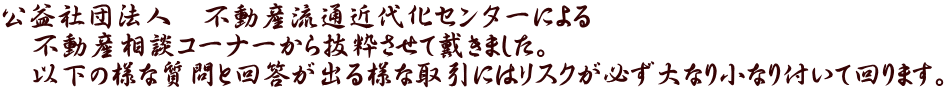
掲載されている回答は、あくまでも個別の相談内容に即したものであることをご了承のうえご参照ください。
掲載にあたっては、プライバシーの保護のため、相談者等の氏名・企業名はすべて匿名にしてあります。
売買事例 0910-B-0107
「公簿売買」における面積の誤差によるトラブル防止法
「公簿売買」で、後日、買主が測量した結果、その面積に誤差が生じることがある。そのような場合に、ある程度以上の誤差が生じるとトラブルになることがあるが、そのようなトラブルを防止するためには、どのようにしたらよいか。
| 事実関係 | |
| 当社は媒介業者であるが、先日行われたある研修会で、土地の「公簿売買」を行った媒介業者が、取引後の測量で面積に約8%の誤差が生じたとの理由でトラブルに巻き込まれたという話が出た。 このような話を聞いていると、我々が日常行っている「公簿売買」という取引方法が本当に有効なのかという疑問が出てくる。 |
|
| 質問 | |
| 1. | この「公簿売買」という取引方法は、本当に法律的にも有効なものなのか。 | |
| 2. | 売買の当事者は、最初から「面積に増減が生じても、代金の清算は行わない」と約束しているのだから、トラブルになるはずがないと思うのだが、なぜトラブルになるのか。営業マンの説明の仕方が悪いのか、あらかじめメジャーを当てるなどの行為をしていなかったからではないのか。 | |
| 3. | その研修会で、講師は、「公簿売買において、一般に許容される誤差の範囲は3%から5%程度ではないか」という意見を述べていたが、この意見は正しいか。 | |
| 回答 | ||
| (1) | 質問1. について—法律的にも有効な取引方法であると考えて差し支えない。ただし、この「公簿売買」には、通常、買主側に面積の増減についての「錯誤」という問題が付いて回るので、個別の取引が有効といえるためには、「公簿売買」についてのリスクを買主が十分認識していることと、結果的に生じる面積の誤差が買主の許容し得る範囲内にあることが前提となろう。 | |
| (2) | 質問2. について—そのとおりで、たとえば、営業の担当者が、あらかじめ買主に対し、「本件の取引は、いわゆる「公簿売買」といって、重要事項説明書や売買契約書には登記簿に記載されている面積が表示されていますが、実際にその面積があるということではなく、測量図がないために登記簿に記載されている面積を表示しているだけなのです。したがって、後日あなたが土地を測量し、その結果、面積に増減が生じても代金の清算はしないという取り決めになりますが、それでよろしいですね」という念押しをした上で、取引に入ることが必要である。その際、その前提として、その土地にメジャー等が当てられるのであれば、それによる簡易計測の結果を図で説明するとか、建物が建て込んでいてメジャーが当てられないのであれば、その旨を買主に伝え、将来のリスクについて十分納得してもらった上で、取引に入っていくという慎重な対応が求められよう。 なお、この場合、営業担当者の簡易計測その他の調査の結果、相当程度以上の誤差が生じることが判明したときは、いったん取引を中止し、再度取引方法を検討するなどの対応も必要となろう。 |
|
| (3) | 質問3. について—必ずしも正しいとはいえない。なぜならば、その取引する土地の種類、用途、価格、購入動機等によって、許容し得る誤差の範囲についての契約当事者の認識が異なると考えられるからである。したがって、たとえば山林や田畑であれば、ほとんどの購入者が土地を見て、「この土地を買う」という認識で購入するであろうから、面積に多少の誤差があっても許容し得ると考えられるが、1m2当たり何十万円とか何百万円という土地であれば、到底そのような認識ではないはずだからである。 | |
| 参照条文 | ||
| ○ 民法第95条(錯誤) 意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。 |
||
| 参照判例 | ||
| ○大判大正7年10月3日民録24巻1852頁(要旨) 法律行為の要素とは、法律行為の主要部分を指し、法律行為の主要部分とは、各法律行為において表意者が意思表示の内容の要部となし、もしこの点につき錯誤がなかったならば意思表示をしなかったであろう場合であり、かつ、表示しないことが一般取引上の通念に照らして妥当と認められるものをいう。 |
||
| 監修者のコメント | |
| 「公簿売買」における面積の誤差によるトラブルは、買主が宅建業者あるいは事業者か、そうではなく一般の素人かによって、その結論が違ってくる可能性が高い。すなわち、「公簿売買」という用語自体の理解が一般素人の場合、「契約書に登記簿面積を記載している」こと程度に考え、実測清算をしないという意味までは含んでいないという認識の人がかなりいる。そこで、宅建業者がプロの知識を前提として当然のごとく、「本件は公簿売買である」との説明をした場合、素人の買主の認識との食い違いからトラブルになる。 したがって、回答(2)のように実測清算をしないことを明確に説明することが必要で、それをしている以上、原則的には誤差の程度いかんにかかわらず、買主は売主や仲介業者に文句を言えない。ただ、売主又は仲介業者が面積に関し、詐欺的言辞たとえば20m2も差異があるのを知りながら、買主に対し「せいぜい2、3m2でしょう」などと言った場合は、例外となると考えられる。 |